共済コラム
中学生の塾通いはいつからがおすすめ?
高校受験対策に向けた選び方
-
こんにちは。ちょこっと共済ライターチームです。
この記事で分かること。
・中学生で塾に通うタイミング
・中学生の塾通いの費用
・中学生の塾の選び方と注意点
中学生の塾通いは必要不可欠?
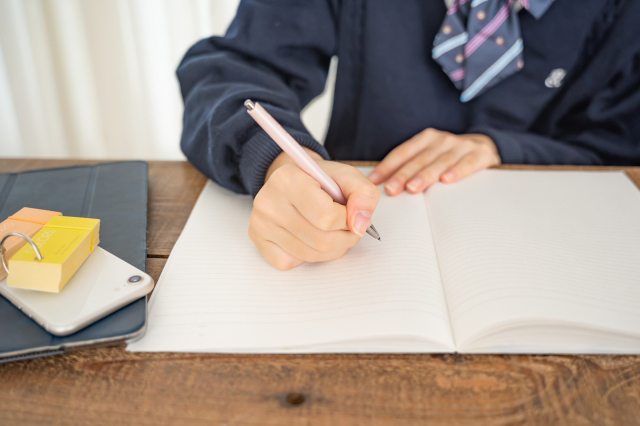
近年、塾通いは高校受験を成功させるために有効な手段の1つです。 自宅での自己学習を苦手とする子どもが多いことや、受験対策が学校の授業だけでは追いつかないという現実が、塾の存在意義を高めているのでしょう。 また家庭教師などの個人指導に比べると費用がかからないため、費用を抑えて効率的に勉強したいという場合に塾は最適と言えます。
学習意欲アップにつながる
塾に通い始めると定期的に勉強する習慣が身に付きやすくなります。 また塾には、勉強や受験に対する意識が高い生徒が集まりやすいため、受験に対する意欲の向上につながるでしょう。 中学生など思春期においては、まわりの環境に影響されることが多いので、勉強に集中できる環境を用意することが大切です。 受験生にとって目標を共有し、ともに勉強できる塾という場所は、良い結果をもたらす可能性を高めてくれる環境と言えるでしょう。
受験以外のサポートが受けられる
塾によっては、受験以外のサポートを受けられるケースもあります。 例えば、子どもの得意教科や資質を考慮してピッタリな高校を紹介してくれたり、カウンセリングを行い、メンタルケアなど精神面でのサポートをしてくれたりする塾もあります。 ただし、これらのサポートは塾によって特徴が異なるため、求めるサポートが受けられる塾を探す必要があるでしょう。
中学生はいつから塾通いをスタートすべき?

何年生から塾に通うかを判断する材料として、通い始めた際のメリットやデメリットを学年別に解説します。
中学1年生
中学1年生で塾通いを始めるメリットは、勉強に充てられる時間が豊富であることです。 高校受験までたっぷり猶予があるため、長期スパンでスケジュールを組むことができます。 とはいえ、学校に入ったばかりの1年生は自己学習の習慣がついていないケースが大半です。 塾へ通うことで、自己学習を習慣化するきっかけになるでしょう。 デメリットは、受験までの期間が長いことでモチベーションを保つことが難しくなり、勉強疲れが起こる可能性があることです。
中学2年生
中学2年生で塾に行くメリットは、3年生になる前に勉強の内容を定着させられる点です。 これまで学んだ勉強内容をしっかりと理解し、定着させることで、本格的な受験勉強の備えとなります。 またこの時期の内申点は受験に大きく影響する可能性があることから、対策が間に合うのもメリットと言えるでしょう。 ただし部活が忙しくなるのはこの時期なので、塾と部活の両立など、生活リズムを整えるまでに時間がかかりやすい点が課題となるでしょう。
中学3年生
中学3年生の多くは、夏頃に部活動を引退するため時間に余裕が生まれます。 その空いた時間をすべて塾に充てられるのは大きなメリットです。 また受験の時期が近付いているため、子どもの意識も変化しており、目標に向かって邁進するでしょう。 デメリットは、受験までの時間が少ないことです。 高校入試は主に1月から3月に行われるため、夏から通うと半年ほどしか猶予がありません。 志望校の合格を目指し、短期間で受験対策に取り組む必要があります。
塾に入るタイミングはいつがおすすめ?

まず、塾に通い始める学年についてお伝えしてきましたが、ここからは塾に通い始めるタイミングについて解説します。
春休みがおすすめ
塾に通い始める時期は春休み頃がおすすめです。 春休みは、4月から学年が切り替わるタイミングのため、夏休みに比べて学校の宿題は少ない傾向があり、部活動の大きな大会も少ないことから塾の勉強を進めやすい時期です。 また、これまで勉強した内容の総まとめができるため、学年が上がる前に苦手を克服できるのもメリットと言えます。
夏休みから通い始めるメリット・デメリット
夏休みは中学校ではもっとも長い休みなので、じっくり勉強できる良い機会です。 多くの塾では夏期講座や合宿など、長時間勉強に集中できる環境を用意しているため、うまく活用すれば、一気に学力を上げられます。 ただし夏休みは、学校の宿題や部活動の大会などが多い傾向が見られるため、人によっては勉強にかける時間を確保しにくいといったデメリットがあります。 そのため、入塾前にスケジュールをよく確認する必要があるでしょう。
冬休みから通い始めるメリット・デメリット
冬休みから塾通いを始め、1学期と2学期の復習をおこなえば、学年末テストでの成績アップが期待できます。 学年末のテストで好成績を達成すれば、次の学年に向けて弾みがつきます。 しかし冬休みは期間が短く、クリスマスや正月などイベントが多いこともあり、勉強に集中しにくい傾向があります。
中学生の塾通いにかかる費用の目安

文部科学省が令和3年度に実施した調査結果によると、中学生の3年間にわたる塾通いの平均費用(年)は、公立校が約25万円、私立校は約17.5万円です。
またこの調査結果から、公立校、私立校とも学年が上がるごとに学習塾にかける費用は増加傾向にあることが分かります。
ほかにも3年生は公立が約39万円、私立で約22万円と、全学年の平均値より大きく上回っていることから、3年生の塾通いが他の学年に比べもっとも多いことが見てとれます。
下記の表は、公立校と私立校の補助学習費(学習塾費)を学年別にまとめたものです。
<中学生における補助学習費(学習塾費)>
| 公立校の補助学習費(円) | 私立校の補助学習費(円) | |
|---|---|---|
| 中学1年生 | 156,032 | 126,795 |
| 中学2年生 | 203,859 | 181,436 |
| 中学3年生 | 389,861 | 219,276 |
| 全学年の平均 | 250,196 | 175,435 |
費用の内訳を確認
塾にかかる費用の中には、毎月の授業料に加えさまざまな費用が含まれています。
主な費用の内訳は下記のとおりです。
・授業料
・入会費・年会費
・教材費
・模試代
・特別講習代(春季・夏期・冬期講習代など)
・設備費
・諸経費
ただし、費用の内訳項目や費用の額は塾によって大幅に変わるため、正確に知りたい場合は事前に確認しておきましょう。
通う塾の選び方を解説

塾は下記の6つの視点から選ぶと良いでしょう。
・塾の方針
・授業形式(集団・個別)
・設備や授業内容
・合格実績
・料金
・サポート体制
具体的に解説していきます。
塾の方針で選ぶ
多くの塾には、独自の特色や性質があります。 具体的には競争させる、褒めて伸ばすなど精神面での方針や、学習方法、目的などです。 一般的な塾は子どもに応じて方針や勉強のスタイルを変えることがないため、雰囲気や方針に合わないと学力が伸びにくい場合もあります。 そのため、子どもの性格や勉強の目的を考慮して塾を選ぶようにしましょう。
授業形式(集団・個別)で選ぶ
塾の授業形式は、主に「集団指導」と「個別指導」の2つに分かれます。 集団指導はクラス単位で授業が行われる授業形式です。 競争心がある子どもに向いており、自分のペースで勉強したい子どもには不向きと言えます。 個別指導は1人、または少人数で授業が行われる授業形式です。 この形式は、自分のペースでしっかり勉強したい子ども向けの方法と言えるでしょう。
設備や授業内容で選ぶ
塾の設備や授業内容を知るために、体験授業に参加するのもおすすめです。 体験授業を受けることで、塾の設備や授業を体験し、塾の雰囲気を感じることができるため、ミスマッチを避けやすくなります。 また、実際に利用する予定の交通機関や道順で塾へ行くことで、通塾ルートや所要時間をチェックすることもできます。
合格実績で選ぶ
合格実績は塾の指導やサポートが受験で生かされているという、一種の証拠のようなものです。 受験対策のノウハウを有している塾は、合格実績が豊富にあります。 とはいえ塾によって得意とする学科や高校があるため、子どもが目標とする高校の合格実績が多い塾を選ぶようにしましょう。 ただし、合格者数が公開されている場合、母数の多い大手の塾がよく見えやすいので注意が必要です。
料金で選ぶ
一般的には、塾に入ると年間20万円~40万円ほどの費用がかかります。 かなり高額な費用ですが、かといって料金が安すぎる塾はサービスの質が気になるところです。 いくら安くても学力アップや受験対策の目的が達成できないと、費用が無駄になってしまうため注意しましょう。 サービスの質と費用のバランスがとれた塾がおすすめです。
サポート体制で選ぶ
子どもの進学・成績アップに向けて、どのようにサポートしていくのかで成果が大きく変わるケースもあります。 個別相談や保護者面談など勉強の指導に加え、トータルでサポートしてくれる塾がおすすめです。 とくに受験のために通塾する場合は進路相談ができる塾を選ぶと、学力に応じた志望校選びや今後のスケジュールなど相談にのってもらえるため、心強いと感じるでしょう。
中学生の塾を選ぶときの注意点

ここからは塾を選ぶときの注意点について解説します。
下記の注意点を押さえておくことで「塾が続かない」、「成果が出ない」といった事態を避けやすくなるでしょう。
・「友達が通っている」という理由だけで選ばない
・料金の安さだけで選ばず、複数を比較検討する
・安全に通えるルートや万が一の対策を調べておく
それぞれ解説していきます。
「友達が通っている」という理由だけで選ばない
塾へ通うのを不安に感じている状況で友達がいると安心感はありますが、子どもに最適な塾は一人ひとり異なります。 現在の学力や、塾へ通う目的が子どもによってそれぞれ違うためです。 そのため、塾に通う目的を明確にし、それに合った塾を選ぶことが大切と言えます。
料金の安さだけで選ばず、複数を比較検討する
料金が安い場合は、何か理由があるかもしれません。 例えば指導者が少ない、受験のノウハウがなく合格実績に乏しいなどが考えられます。 あるいは、設備が古い、空調設備が整っていないなど、勉強の集中を妨げるような環境なのかもしれません。 料金の高い塾がよいわけではありませんが、しっかりと中身を確認することが重要です。
安全に通えるルートや万が一の対策を調べておく
塾に通うと夜遅くに帰ることが多くなるため、安全面を事前に注意しておく必要があります。 特に送り迎えがない場合は、帰りの時間帯を中心に塾の周辺環境を下調べすることをおすすめします。 街灯は十分か、人通りはどのくらいあるかなどを把握し、安全なルートを探しましょう。 また万が一のことを考えてGPSや防犯ブザーの所持など、防犯について家族で話し合っておくと安心感が増すでしょう。
まとめ

中学生になると、学校の授業が難しくなってきます。また、高校受験を意識し始める時期でもあるため、塾に通い始める人も多いです。 とはいえ、塾といっても学校で学ぶ内容のサポートや難関校の受験対策など、さまざまなタイプに分かれています。 子どもの学力や性格、目的に応じて最適な塾を選ぶことが大切です。 また塾通いには、安全面も考慮する必要があります。 とくに自転車で塾に通う場合は、事故のリスクが上がるため、十分に注意して通塾しましょう。
ちょこっと共済は、東京都の39市町村が共同で運営する公的な交通災害共済で、交通事故に遭い治療を受けた会員に対して見舞金を支給する制度です。
東京都の市町村に住民登録のある方なら年齢・健康状態に関係なくどなたでも加入することができ、会費は年額1,000円または500円と大変安価です。
万が一の事故に備えて、お守り代わりにぜひご加入されてはいかがでしょうか。

おすすめ記事
-

【大人向け】自転車乗車中はヘルメット着用が義務?罰則や正しい着用方法・選び方を解説
-

【大人向け】自転車に乗れない理由とは?乗れない人必見のおすすめ練習法とコツを解説
-
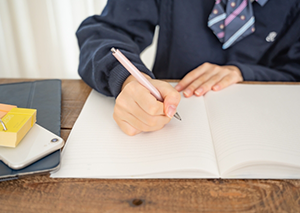
中学生の塾通いはいつからがおすすめ?高校受験対策に向けた選び方
-

【ペーパードライバー向け】ドライバー保険とは?補償内容やメリット・デメリットを解説
-

共済加入がおすすめの人とは?生命保険との違い、比較ポイント、選び方を解説
-

自転車事故のリスクと保険の必要性|自転車事故の賠償例・自転車保険の保障内容を徹底解説
-

交通事故に遭った場合の保険金|受け取れる慰謝料の種類や相場、支払いまでの流れなど解説
-

通学中の怪我に対応する保険とは?災害共済給付制度について給付対象など詳しく解説

